飲食回数とむし歯について “何を食べるか”だけでなく“何回食べるか”もカギだった!?
虫歯予防といえば、「甘いものを控えましょう」というアドバイスがよく聞かれますが、実は“飲食の回数”も”むし歯発生の大きな要因”であることをご存じでしょうか?
回数が増えるほど、お口の中が酸性の状態にさらされ、歯が溶けやすくなります。つまり、「食べ方の習慣」がむし歯リスクを大きく左右しているのです。正しい知識を持って、“回数管理”を意識した食生活を送ることが、歯を守る第一歩になります。
■ 目次
- むし歯のメカニズムと飲食の関係
- なぜ“回数”が問題なのか?
- 間食の落とし穴:隠れたリスクに気づこう
- 飲み物も要注意!“ダラダラ飲み”の落とし穴
- 今日からできる、むし歯を防ぐ食習慣のコツ
1. むし歯のメカニズムと飲食の関係
むし歯は、**口腔内の細菌(主にミュータンス菌)**が食べ物の糖分をエサにして酸を作り、その酸が歯を溶かすことで発生します。これを「脱灰(だっかい)」と呼びます。
通常、唾液の力によって口の中のpHは中性に戻り、歯の表面も再び修復(再石灰化)されます。
しかし、飲食の回数が多いと口内が常に酸性に保たれてしまい、再石灰化が間に合わず、むし歯が進行してしまうのです。
つまり、「食べる=酸性状態になる」→「回数が多い=酸の時間が長い」という悪循環が、むし歯のリスクを高めるのです。
2. なぜ“回数”が問題なのか?
ここで重要なのは、「砂糖を摂取すること」よりも「どれだけ頻繁に摂取するか」です。
以下は、ある1日を例にした口腔内のpH変動です:
- 朝食 → pHが急降下(酸性)
- コーヒーとクッキーを10時に → 再び酸性に
- 昼食 → 酸性状態に
- 3時のおやつ → さらに酸性時間が延長
- 夕食後のデザート → 再度酸性
- 夜の晩酌やアイス → 最後まで酸性に…
このように「小分けの飲食」が多いと、1日中、歯が酸にさらされている時間が長くなり、再石灰化のチャンスがなくなるのです。
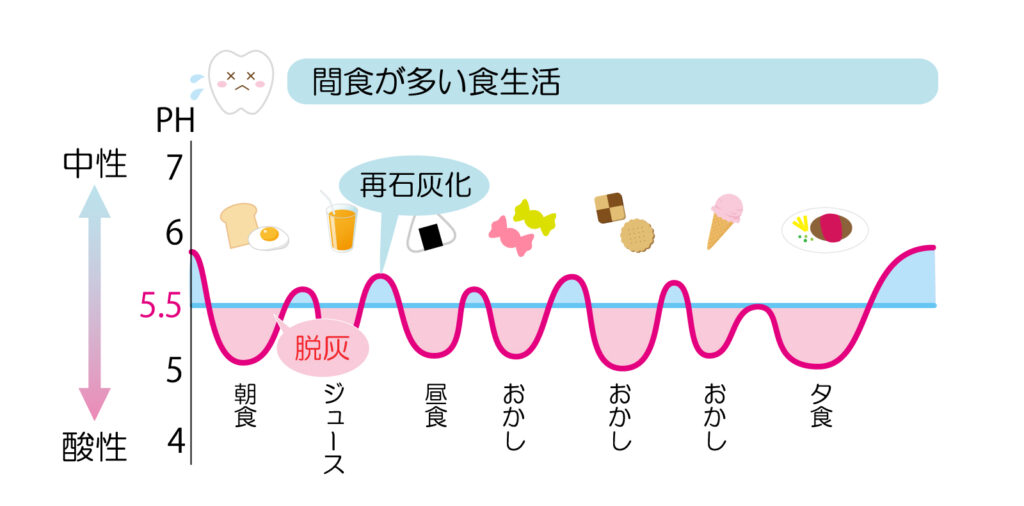
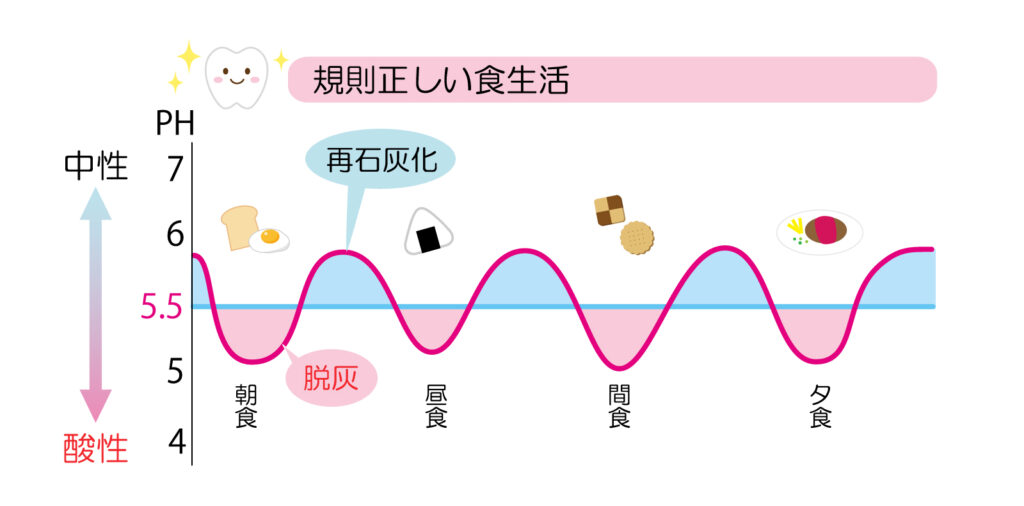
3. 間食の落とし穴:隠れたリスクに気づこう
特に見落とされがちなのが、子どもの間食や、仕事中のちょこちょこ食べです。
「グミやチョコを1個だけ」「せんべいをちょっとつまむ」など、少量であっても口にするたびに口腔内は酸性になり、その都度、歯がダメージを受けています。
また、保護者の方の中には、「甘くないから大丈夫」とポテトチップスやクラッカーを与えるケースもありますが、デンプンも分解されれば糖質になり、むし歯の原因になるのです。
「ちょっとだけだからいいや」が重なると、結果として1日中ずっと“脱灰”が続いてしまう危険性があります。
4. 飲み物も要注意!“ダラダラ飲み”の落とし穴
実は、飲み物の飲み方にも注意が必要です。
・スポーツドリンク
・ジュース類
・砂糖入りコーヒーや紅茶
・ミルクティーや甘酒
これらの飲料を時間をかけてちびちび飲むことは、想像以上に口の中を酸性に保つ原因になります。飲み物=液体=洗い流されるというイメージがありますが、甘い飲料は歯の表面に長く残留しやすく、むし歯のリスクが高くなります。
水やお茶は問題ありませんが、甘い飲み物はできるだけ時間を区切って、まとめて飲み終える習慣が大切です。
5. 今日からできる、むし歯を防ぐ食習慣のコツ
では、むし歯を防ぐために、どのような飲食習慣を心がければよいのでしょうか?以下に具体的なポイントを紹介します。
- 飲食は1日3回+間食1回以内に抑える
- 間食は時間と量を決めて「イベント化」する(例えば15時のおやつタイム)
- 甘い飲み物はまとめて飲むようにし、ちびちび飲みはしない
- 間食の後は歯磨きをする、水で口をゆすぐ
- 寝る前は絶対に飲食しない(唾液の分泌が減り、むし歯リスク大)
また、定期的な歯科検診によって、初期虫歯の発見やブラッシング指導を受けることも重要です。
■ まとめ
むし歯は「甘いものを食べたらできる」ものではなく、“飲食の回数が多いこと”が最大のリスクになります。
言い換えれば、「何を食べるか」以上に「どう食べるか」が大切なのです。
現代社会では、いつでも食べられる・飲める環境が整っています。だからこそ、食の“回数”に意識を向けることが、むし歯予防の鍵となります。
少しの習慣の見直しが、あなたの歯の未来を大きく変えるかもしれません。
ぜひ、今日から「お口の時間割」を意識してみてくださいね。
歯を守る第一歩は、“ちょこちょこ食べ”をやめることから。
気になることがあれば、ぜひ歯科医院でお気軽にご相談ください。
歯科衛生士 田中
